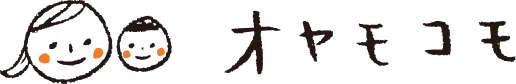経理規程
第1条(会計処理の原則) この法人の会計は、法令、定款及びこの規程の定めるところに
よるほか、一般に公正妥当と認められる一般財団法人の会計の慣行に準拠して行わなけ
ればならない。
第2条(会計区分) この法人の会計について、法令の要請等により必要とされる場合
会計区分を設けるものとする。
第3条(経理責任者) 経理責任者は、代表取締役 山下千春とする。
第4条(勘定科目の設定) この法人の会計においては、財務及び会計のすべての状況を的
確に把握するため必要な勘定科目を設ける。
第5条(会計帳簿) この法人の会計帳簿は、次のとおりとする。
(1) 主要簿
ア 仕訳帳
イ 総勘定元帳
(2) 補助簿
ア 現金出納帳
イ 預金出納帳
ウ 固定資産台帳
エ 基本財産台帳
オ 特定資産台帳
カ 会費台帳
キ 指定正味財産台帳
ク その他必要な勘定補助簿
第6条(証憑)証憑とは、当団体の内部または外部で発行される書類で取引の裏付けとなる
ものをいい、請求書、領収書、契約書、電算出力帳票、その他会計伝票の正当性を立証す
る書類をいう。
第7条(帳簿の更新)帳簿は、原則として毎月末日に締切り、会計年度ごとに更新する。
第8条(帳簿書類の保存期間)経理関係書類の保存期間は、次のとおりとする。ただし、法
令が定める期間がこれを超えるものについては、その定めによる。
(1) 決算書類 永久
(2) 予算書 10年
(3) 会計帳簿・会計伝票 10年
(4) 契約書・証憑書類 10年
(5) その他の書類 10年
2 収支予算書は、正味財産増減計算書に準ずる様式をもって作成する。
第9条(金銭の範囲) この規程で金銭とは、現金及び預貯金をいい、現金とは通貨のほか、
随時に通貨と引き換えることができる小切手・手形及び証書等をいう。
第10条(出納責任者) 金銭の出納・保管については、出納責任者を置くものとする。
2 出納責任者は、経理責任者が任命する。(出納責任者:細川 都)
3 出納責任者は、金銭の保管及び出納事務を取扱わせるため、出納事務の担当者を若干
名置くことができる
第11条(金銭の出納) 金銭の出納について、出納責任者が承認した証憑に基づいて行う。
第12条(支払手続) 出納事務の担当者が金銭を支払う場合には、最終受取人からの請求
書その他取引を証する書類に基づいて、支払伝票により出納責任者の承認を得て行うも
のとする。
第13条(固定資産の範囲) 固定資産とは、耐用年数1年以上で、かつ、取得価額10万
円以上の有形固定資産およびその他の資産とする。
第14条(取得価額) 固定資産の取得価額は次の各号による。
(1) 購入に係るものは、その購入価格に付随費用を加算した額
(2) 贈与によるものは、そのときの適正な評価額
第15条(固定資産の管理責任者) 固定資産の管理責任者は、経理責任者とする。
第16条(固定資産の管理) 固定資産の管理責任者は、固定資産及び物品について、台帳
を設け、その記録及び管理を行うものとし、各会計年度において、必ず全固定資産を対象
令が定める期間がこれを超えるものについては、その定めによる。
(1) 決算書類 永久
(2) 予算書 10年
(3) 会計帳簿・会計伝票 10年
(4) 契約書・証憑書類 10年
(5) その他の書類 10年
2 収支予算書は、正味財産増減計算書に準ずる様式をもって作成する。
第9条(金銭の範囲) この規程で金銭とは、現金及び預貯金をいい、現金とは通貨のほか、
随時に通貨と引き換えることができる小切手・手形及び証書等をいう。
第10条(出納責任者) 金銭の出納・保管については、出納責任者を置くものとする。
2 出納責任者は、経理責任者が任命する。(出納責任者:細川 都)
3 出納責任者は、金銭の保管及び出納事務を取扱わせるため、出納事務の担当者を若干
名置くことができる
第11条(金銭の出納) 金銭の出納について、出納責任者が承認した証憑に基づいて行う。
第12条(支払手続) 出納事務の担当者が金銭を支払う場合には、最終受取人からの請求
書その他取引を証する書類に基づいて、支払伝票により出納責任者の承認を得て行うも
のとする。
第13条(固定資産の範囲) 固定資産とは、耐用年数1年以上で、かつ、取得価額10万
円以上の有形固定資産およびその他の資産とする。
第14条(取得価額) 固定資産の取得価額は次の各号による。
(1) 購入に係るものは、その購入価格に付随費用を加算した額
(2) 贈与によるものは、そのときの適正な評価額
第15条(固定資産の管理責任者) 固定資産の管理責任者は、経理責任者とする。
第16条(固定資産の管理) 固定資産の管理責任者は、固定資産及び物品について、台帳
を設け、その記録及び管理を行うものとし、各会計年度において、必ず全固定資産を対象
第8条(帳簿書類の保存期間)経理関係書類の保存期間は、次のとおりとする。ただし、法
令が定める期間がこれを超えるものについては、その定めによる。
(1) 決算書類 永久
(2) 予算書 10年
(3) 会計帳簿・会計伝票 10年
(4) 契約書・証憑書類 10年
(5) その他の書類 10年
2 収支予算書は、正味財産増減計算書に準ずる様式をもって作成する。
第9条(金銭の範囲) この規程で金銭とは、現金及び預貯金をいい、現金とは通貨のほか、
随時に通貨と引き換えることができる小切手・手形及び証書等をいう。
第10条(出納責任者) 金銭の出納・保管については、出納責任者を置くものとする。
2 出納責任者は、経理責任者が任命する。(出納責任者:細川 都)
3 出納責任者は、金銭の保管及び出納事務を取扱わせるため、出納事務の担当者を若干
名置くことができる
第11条(金銭の出納) 金銭の出納について、出納責任者が承認した証憑に基づいて行う。
第12条(支払手続) 出納事務の担当者が金銭を支払う場合には、最終受取人からの請求
書その他取引を証する書類に基づいて、支払伝票により出納責任者の承認を得て行うも
のとする。
第13条(固定資産の範囲) 固定資産とは、耐用年数1年以上で、かつ、取得価額10万
円以上の有形固定資産およびその他の資産とする。
第14条(取得価額) 固定資産の取得価額は次の各号による。
(1) 購入に係るものは、その購入価格に付随費用を加算した額
(2) 贈与によるものは、そのときの適正な評価額
第15条(固定資産の管理責任者) 固定資産の管理責任者は、経理責任者とする。
第16条(固定資産の管理) 固定資産の管理責任者は、固定資産及び物品について、台帳
を設け、その記録及び管理を行うものとし、各会計年度において、必ず全固定資産を対象として、
令が定める期間がこれを超えるものについては、その定めによる。
(1) 決算書類 永久
(2) 予算書 10年
(3) 会計帳簿・会計伝票 10年
(4) 契約書・証憑書類 10年
(5) その他の書類 10年
2 収支予算書は、正味財産増減計算書に準ずる様式をもって作成する。
第9条(金銭の範囲) この規程で金銭とは、現金及び預貯金をいい、現金とは通貨のほか、
随時に通貨と引き換えることができる小切手・手形及び証書等をいう。
第10条(出納責任者) 金銭の出納・保管については、出納責任者を置くものとする。
2 出納責任者は、経理責任者が任命する。(出納責任者:細川 都)
3 出納責任者は、金銭の保管及び出納事務を取扱わせるため、出納事務の担当者を若干
名置くことができる
第11条(金銭の出納) 金銭の出納について、出納責任者が承認した証憑に基づいて行う。
第12条(支払手続) 出納事務の担当者が金銭を支払う場合には、最終受取人からの請求
書その他取引を証する書類に基づいて、支払伝票により出納責任者の承認を得て行うも
のとする。
第13条(固定資産の範囲) 固定資産とは、耐用年数1年以上で、かつ、取得価額10万
円以上の有形固定資産およびその他の資産とする。
第14条(取得価額) 固定資産の取得価額は次の各号による。
(1) 購入に係るものは、その購入価格に付随費用を加算した額
(2) 贈与によるものは、そのときの適正な評価額
第15条(固定資産の管理責任者) 固定資産の管理責任者は、経理責任者とする。
第16条(固定資産の管理) 固定資産の管理責任者は、固定資産及び物品について、台帳
を設け、その記録及び管理を行うものとし、各会計年度において、必ず全固定資産を対象として、
現物と固定資産台帳との照合を実施する。
第17条(固定資産の取得及び処分等) 固定資産の取得、売却及び処分等については、理
事長の決裁を受けなければならない。
第18条(予算の目的) 予算は、各会計年度の事業計画を明確な計数的目標をもって表示
し、もって、事業の円滑な運営を図ることを目的として、収支の合理的な規制を行うもの
である。
第19条(収支予算の作成) 収支予算は、事業計画に基づき、毎会計年度開始前に代表取
締役が作成し定める。
第20条(収支予算の執行) 各事業年度における費用の支出は、収支予算書に基づいて行
うものとする。
第21条(決算の目的) 決算は、一会計期間の会計記録を整理し、財務及び会計のすべて
の状態を明らかにすることを目的とする。
第22条(決算整理事項) 経理責任者は、毎会計年度終了後速やかに、当該会計年度末に
おける次の財務諸表書類を作成し理事会に提出しなければならない。
(1) 貸借対照表
(2) 損益計算書(正味財産増減計算書)
(3) 計算書類(貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)をいう。)の付属書
類
(4) 財産目録
事長の決裁を受けなければならない。
第18条(予算の目的) 予算は、各会計年度の事業計画を明確な計数的目標をもって表示
し、もって、事業の円滑な運営を図ることを目的として、収支の合理的な規制を行うもの
である。
第19条(収支予算の作成) 収支予算は、事業計画に基づき、毎会計年度開始前に代表取
締役が作成し定める。
第20条(収支予算の執行) 各事業年度における費用の支出は、収支予算書に基づいて行
うものとする。
第21条(決算の目的) 決算は、一会計期間の会計記録を整理し、財務及び会計のすべて
の状態を明らかにすることを目的とする。
第22条(決算整理事項) 経理責任者は、毎会計年度終了後速やかに、当該会計年度末に
おける次の財務諸表書類を作成し理事会に提出しなければならない。
(1) 貸借対照表
(2) 損益計算書(正味財産増減計算書)
(3) 計算書類(貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)をいう。)の付属書
類
(4) 財産目録
以上
附 則
この規程は、2025年2月1日から施行する。
投稿日:2025年02月21日